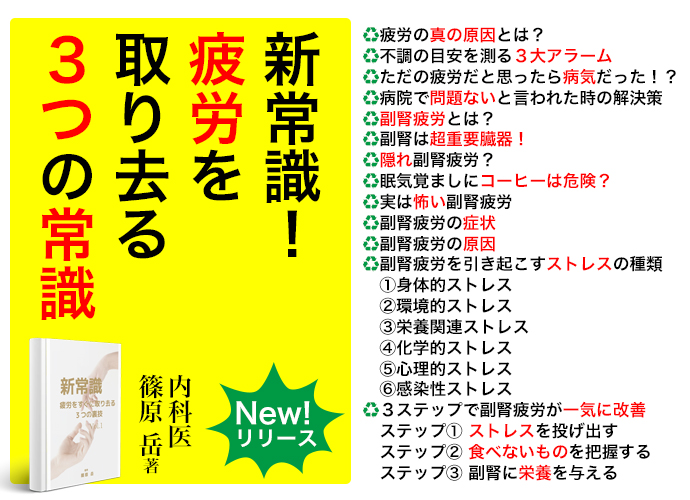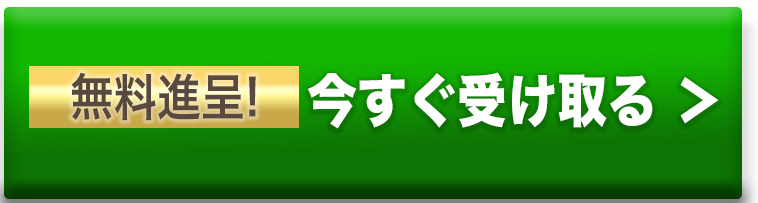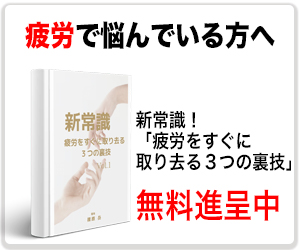表参道・原宿の東京原宿クリニック 院長の篠原です。
お腹が張ってしまったり、下痢や便秘で苦しいということでお悩みの方もいらっしゃることと思います。
お腹のことについては、本人としては、昔からそんなものだろう、と放っている人も多いです。
そして、お腹の張りを良くしようと、最近はやりの”腸活”を行った結果、もっと悪くなってしまったり、内科でもらった薬でさらにお腹がはってしまったりする方もいらっしゃいます。

最近、このような症状で、SIBO(シーボ:小腸内細菌増殖症)と考えられる方が増えているような気がします。
SIBOは比較的新しく言われている概念なので、消化器内科医でも知らない人もいらっしゃいます。
また、放おって置くと、腸から異物が体内に入り込んでアレルギーを起こしたり、栄養を吸収できないなどの弊害が続きます。

今回は、腸の弱い方がやたらと腸活することによって、逆にお腹の張りが悪化する可能性があることと、放置することの危険性、その対処法をお話したいと思います。
公式LINEでは、体調不良などの症状の改善のヒントとなる情報を配信しています。また、随時お得なクーポンなども配布しております。是非公式LINEにご登録ください。
Contents
お腹が張って仕方がないという患者さん
ある日、内科外来にお腹が張って仕方がない、という患者さんがいらっしゃいました。
すでに、その患者さんはお腹のことについては別の消化器内科にかかっており、治療中だとのことでした。
しかし、治療中であるけれど、良くならず、かえって悪化していて困っているとのことでした。
お腹を触ってみると、どうも空気が溜まっているような感じでした。
お聞きすると、
- 食事後にお腹が張る。
- 家族に、腸を良くするのが大事だと言われて、ヨーグルト、キムチ、納豆を多く摂るように言われて、頑張っている。
- 最近、自分の吐く息がとても臭くて、気になっている。
- 消化器内科で上部消化管内視鏡をされて、逆流性食道炎と言われた。
- 薬としては、ビオスリー(プロバイオティクス)、タケキャブ(胃酸抑制剤)、ブスコパン(腸管痙攣止め)を処方されているが、良くならない。
- 今度、大腸カメラを予約している。

という状況であることがわかりました。
このお話から、普段は腸内細菌があまり多くない小腸に、腸内細菌が異常増殖してしまったためにおこる、SIBO(シーボ:小腸内細菌増殖症)が思い浮かびました。
最近、腸活ブームの影響なのか、SIBOを経験することが多くなってきたように感じます。
SIBOについて、お話してみたいと思います。
SIBOとは
SIBO(小腸内細菌増殖症)とは、その名前の通り、小腸の中で細菌が増えすぎてしまう状態のことを言います。
大腸には1mlあたり10の10乗個ほどの細菌が住んでいるのに対して、小腸には1万個(10の4乗個)ほどしか細菌がもともと住んでいません。
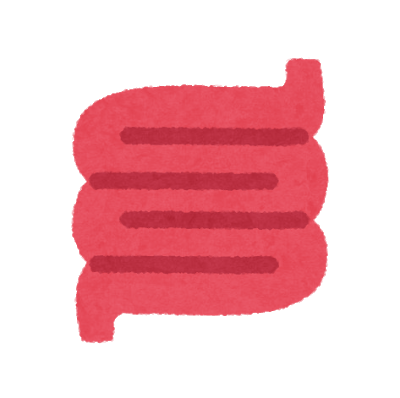
しかしながら、何らかの不具合で小腸の細菌が増えると、10万個以上になり、腹部膨満感などの症状を引き起こして、それをSIBOと言うのでした。
SIBOになると、何が困るのでしょうか。
自覚症状的には
小腸に増えた細菌がガスを大量に発生して、お腹が張ります。
お腹に溜まったガスが、食道に戻ってきて、逆流性食道炎をおこします。ゲップや息が臭いなどを引き起こすわけです。
腸内環境が悪いために、便秘や下痢をひき起こします。
腸粘膜へのダメージ
細菌が小腸に増えてしまい、細菌を包んでいるバイオフィルムや、毒素が小腸の粘膜を傷つけます。
そのことにより、腸漏れ症候群(リーキーガット症候群)の原因になります。
腸漏れ症候群(リーキーガット症候群)とは、通常では入っていかない毒素などが、腸粘膜を通過して、血液の中に侵入することにより、アレルギー症状などの不具合を起こすことをいいます。
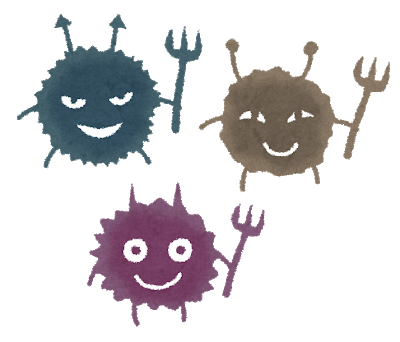
慢性的にアレルギー反応が続いていると、副腎がそれを消そうとして、副腎疲労の原因ともなります。
栄養の吸収障害
せっかく食べた栄養が、小腸で増えた細菌に横取りされることによって、栄養素不足になってしまいます。
アミノ酸、ビタミンやミネラルなどが吸収されず、エネルギーを作るために必要な栄養素が足りなくなるために、副腎疲労などの多彩な症状が出てしまうことになるわけです。
もし、あなたがお腹が張るという症状以外に、疲れやアレルギー、不眠などの全身の色々な症状があるのであれば、SIBOは疑ったほうがいいかもしれません。
SIBOにはどうしてなるのでしょうか。
SIBOになる原因はいくつかあります。その主なものをあげます。
1.MMC(migrating motor complex)がうまく働かない
MMCとは、胃から始まる腸の収縮運動のことを言います。
MMCのおかげで、胃や小腸内の食べ物ののこりかすや細菌が押し流されます。
MMCが炎症や感染、抗生剤などによってうまく働かないと、食べ物ののこりかすが小腸に残ることになり、SIBOの原因となります。
2.回盲弁がうまく働かない
大腸から小腸への細菌の逆流を防止する機能が障害されると、SIBOになります。
手術や炎症、がんなどによって、回盲弁が働かなくなってしまいます。
回盲弁とは、小腸と大腸の境界にある弁のことです。
回盲弁が働かないと、大腸から小腸へ細菌が逆流してしまうのです。
盲腸をとっている方もいらっしゃると思いますが、手術後には回盲弁が障害されてしまうために、逆流が起こりやすくなってしまいます。
3.胃酸や胆汁の分泌低下
胃酸は、細菌を死滅させるために重要です。
胃酸抑制剤などを飲んでいると、胃酸がうまく効かなくなり、その結果、小腸で細菌が増殖してしまいます。
胸焼けやげっぷがあると、よく、逆流性食道炎の診断で胃酸抑制剤が処方されますが、実はSIBOによりガスが逆流して逆流性食道炎になっていることも多いです。
そのような状態のときに、胃酸抑制剤が処方されると、さらにSIBOが悪化してしまうことがあるわけです。

上に挙げた患者さんも、逆流性食道炎という診断に対して胃酸抑制剤が処方されていて、かえってSIBOが悪化したように感じられました。
また、胆汁も、細菌を増やさないために重要な役割をしています。
胆汁は、胆嚢の中で濃縮されてから、小腸に分泌されます。
胆汁は胆嚢で十分濃縮されることで、はじめて抗菌作用を持つようになります。
よって、胆嚢摘出術を行い、胆嚢が無い方は、SIBOになりやすくなるわけです。
SIBOを疑う方法
症状から疑う
小腸の中に大量のガスが発生するために、腹部膨満感、ゲップ、腹痛が生じます。

腸内環境悪化のため、下痢や便秘、またはそれを繰り返すことが起こります。
このような症状があれば、SIBOの可能性があります。
そのような腹部膨満感が、特定の食事を食べた後にでてくる、といった場合は、さらに確率が高くなります。
特定の食事とは、小腸内で吸収されにくい、発酵性のもの(ヨーグルトやキムチ)などが多いようです。
呼気検査を行う
上に上げたような症状がある場合は、呼気検査を行うことがすすめられています。
小腸で増えた細菌は、水素ガスとメタンガスを作るようになります。
そのため、吐いた息の水素ガスとメタンガス濃度を図ることで、SIBOかどうか判定できるというわけです。

ただ、現在保険が使えないので、一部の自費施設で行うことになります。
さらに、どのような菌が腸内で増殖しているかをみるために、次の便検査を行うことが増えてきています。
便検査や尿検査を行う
近年、便検査も進歩してきて、GIMAP(Gastrointestinal Microbial Assay Plus)という、「定量的リアルタイムPCR検査」を用いて、腸の中の状態を詳しく調べられるようになってきました。
遺伝子検査(DNA)を用いた解析であるために、微量なものも正確に測定できます。

この検査では、腸内細菌のバランス、病原菌、ピロリ菌、善玉菌の状態、日和見菌の状態、消化吸収能力、腸の炎症状態、腸管の免疫状態が一覧的にわかります。
そのため、SIBOになっている原因として、善玉菌が多いのか、日和見菌が多いのか、ピロリ菌が悪さをしているのかなどが目で見てわかるため、それに沿って対処する、ということができるようになってきました。
こちらの検査は、保険診療では行うことができません。
GIMAPについては、こちらもご参照ください。
ただ、欠点として、お腹の張りやすいカビの一種であるカンジダを見つける能力が低いとされているので、カンジダを見つけるためには、別の検査を併用することもおすすめしています。
カンジダを見つけるために有用な検査の1つとして、尿中有機酸検査があります。
尿中有機酸検査につきましては、こちらを御覧ください。
当院では、腹部膨満という症状の場合でおすすめすることが多いのは、GIMAP検査と有機酸検査ということになります(症状によって変わることもあります)。
SIBOをどうやって治すのでしょうか
食事を変える
なんと言っても、小腸の中の細菌が増えないような食事に変更することが必要です。
小腸の細菌を増殖させてしまう食事を、FODMAP(フォドマップ)と言います。
FODMAPとは、発酵性のオリゴ糖、二糖類(乳糖)、単糖類(果糖)、ポリオールのことで、小腸での吸収が悪いがために、細菌が増殖してしまうのです。
ですので、治療は、FODMAPを避ける、低FODMAP食がすすめられます。
低FODMAP食について、詳しい本はこちら。

難点は、低FODMAP食を厳密にやろうとすると、食べてはいけない食品を厳密に選ぶのがとても大変ということに気づきます。
ですので、最初は、小麦を抜く(グルテンフリー)、カゼインを抜く(カゼインフリー)ということを基本にして、後は、食べて腹部膨満感が出てしまう食事を避ける、といった方法でもよいかと思われます。
抗生剤やサプリメント
食事を変更して、それだけで良くなる方もいらっしゃいます。
そういう場合、少しずつ食事を戻していって、大丈夫なことを確認しながら、食べる範囲を増やしていってもいいでしょう。
改善しなかった場合は、やはり医療機関で、増えすぎた細菌を抑える抗生剤や、抗菌ハーブを使用することになります。

しかしながら、保険適応ではないため、SIBOを診療している医療機関で自費で行う必要があります。
当院では、SIBOと診断されたあと、抗生剤やハーブを中心に必要とされる方には除菌しております。
使用する抗生剤につきましては、当院では先程申し上げた、GIMAPという便検査を行い、腸内で増殖している菌種を特定して、その菌に合った薬などを選択しています。
一般的に、先程画像で出てきた、(リフキシマ)リファキシミンは、Methanobacteriacesaeという菌が検出された時に用います。
SIBO除菌が困難なパターン
SIBOの除菌が難しい点は、SIBOになった原因を検索して、そこも治療しないと良くならないことがあります。
多くの場合は、胃酸の分泌が低下しているため、胃で十分殺菌できずに、小腸で細菌が増殖してしまいます。
胃酸の低下の原因として多いのは、胃酸抑制剤の使用や、低血糖により交感神経が緊張して胃が動かなくなることや、ピロリ菌の存在、ストレス、副腎疲労があります。
低血糖については、以下の記事を参考にしてください。
ピロリ菌の存在も大きな問題となります。
ピロリ菌と聞いて、「私は内視鏡を受けて、いないと言われた、血液検査で大丈夫と言われた」という場合でも、精密な便検査(GIMAP)を行うとピロリ菌が検出されることが多く、それを除菌することで、解消される方もいらっしゃいます。
当院では、SIBOの方には、ピロリ菌の検出(GIMAP)に力を入れています。
また、ストレスが多い方は、腸の動きが悪く、例えば、仕事が忙しすぎると、どうしてもSIBOは改善しません。
その場合は、生活習慣そのものを改める必要も出てきます。
副腎疲労がベースにあると、エネルギー不足になるため、これもやはり胃酸の低下を招き、SIBOになりやすくなります。
副腎疲労がある場合は、そちらのケアも必要になってきます。
腸にカンジダというカビの一種が増えることでも腹部膨満になります。
この場合、SIBOの治療と一緒にカンジダを除菌することも必要になってきます。
カンジダについては、こちらもご参考にしてください。
腸をウォッシュアウトする
厳密には、これは治療ではないのですが、大腸カメラの前処置で、下剤を飲むことにより、腸内の細菌が洗い流され、SIBOが良くなる方もいらっしゃいます。
先ほど挙げた患者さんも、大腸カメラを行った後に、症状が良くなったとおっしゃられました。
腸の弱い人が、むやみに腸活することは危険
腸活は、元来胃腸が強い人が行う分には、とてもいい効果をおよぼします。
胃腸が強いとは、胃酸がしっかりと出て、腸内環境が良く、消化酵素もしっかりと出ていて、食べたものがちゃんと消化できている方のことを言います。
下痢や便秘で悩んでいるという方が、腸活を行うことは、SIBOを悪化させるという、リスクがすくなからずあります。
何らかの不調を感じることがあれば、信頼できるところで相談していただければと思います。
当院では、保険診療では検査も治療も行えないため、保険診療ではSIBO治療は行っておりません。
SIBOは栄養外来(栄養療法)(自費診療)で診療しております。
栄養療法については、以下をご参考にしてください。
また、栄養療法を受診する前に、当院がどのような治療方針で行っているかや、費用面などを聞いてから治療を受けるか検討したいという場合は、総合カウンセリングをまず受けていただくことを推奨しております(オンラインでも可能です)。
まとめ
お腹が張り気味が続いている場合、SIBOの可能性があります。
SIBOを放って置くと、栄養吸収が悪化し、全身に悪影響が出ます。
また、疲労などの体調不良がなかなか抜けない方は、公式LINEにご登録下さい。
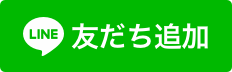
最後に(免責)
本記事の内容は、医学的治療に置き換わるものではありません。個人的にお試しになり健康被害が生じても、当院では一切責任を負えませんのでご了承下さい。
病態の改善に必要な食事・サプリメントはひとりひとり異なります。
基本的に、主治医と相談しながら治療を進めていただければと思います
参考文献
Losurdo G, et al. J Neurogastroenterol Motil. 2020 Jan 30;26(1):16-28.
(2)パン・豆類・ヨーグルト・りんごを食べてはいけません ―世界が認めたおなかの弱い人の食べ方・治し方 江田証
無料レポート新リリースしましたのでお受け取りください!